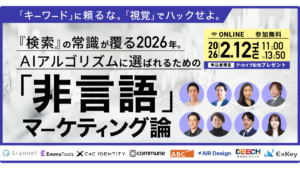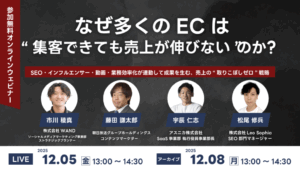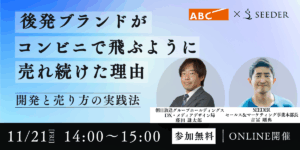【今さら聞けない】動画広告とは?メリットや相性のいい業界、効果を高めるポイントも解説
YouTubeなどの動画プラットフォームやSNSの普及によって、「動画広告」の需要や市場規模が拡大しています。しかし、「Web広告の中でも動画広告を制作するのは難しいのではないか?」「普通の広告と何が違っていて、どんな効果が出るのか?」など疑問に思う方もいるかもしれません。
そこで今回は、Web広告における動画広告のメリットや相性のいい業界、効果を高めるポイントについてご紹介します。動画広告の出稿に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
Web広告における動画広告とは?
動画広告は、Web広告の中でも近年需要が伸び、市場規模も拡大している広告手法の1つです。株式会社サイバーエージェントが実施した調査によると、2023年の動画広告市場は昨年対比112%の6,253億円に到達したことがわかっています。さらに、2024年は7,209億円、2027年には1兆228億円にまで達する見込みであり、今後も市場規模は拡大していくと予想されています。
出典元:サイバーエージェント、2023年国内動画広告の市場調査を発表
動画広告にはいくつかの種類がありますが、主にインストリーム広告・アウトストリーム広告の2種類に分類することが可能です。ここで、動画広告の種類についても解説していきましょう。
インストリーム広告
インストリーム広告とは、動画配信サイトに投稿されたコンテンツ内に配信できる動画広告です。静止画のバナー広告とは異なり、画面全体で商品・サービスをPRできます。インストリーム広告はYouTube以外だとFacebookでも配信することが可能です。
インストリーム広告は動画内のどこで配信されるかによって、3種類に分類できます。
- プレロール広告
- ミッドロール広告
- ポストロール広告
プレロール広告
プレロール広告とは、動画コンテンツが始まる前に表示される動画広告です。視聴者は動画を見るために広告も視聴することになるため、ユーザーからの注目を集めやすく、認知度が高まりやすいというメリットがあります。
また、プレロール広告はさらに細分化することも可能です。一定時間を経過するとスキップできる「スキッパブル広告」や、動画広告をスキップできないが再生時間が15秒以内と短い「ノンスキッパブル広告」があります。さらに、スマホなどのモバイル端末から視聴するユーザーに向けて6秒間の広告を配信する「バンパー広告」もプレロール広告の1つです。
ミッドロール広告
ミッドロール広告とは、動画コンテンツを視聴している途中に配信される動画広告です。動画を見ている途中で配信されるため、続きが気になる視聴者は広告も最後まで視聴してくれる傾向にあります。細かいターゲティングを行うことにより、自社が特に広告を届けたいユーザーに対して動画広告を完全視聴してもらうことも可能です。ミッドロール広告も、プレロール広告と同様に、スキッパブル広告やノンスキッパブル広告、バンパー広告に分けられます。
ミッドロール広告は、動画を配信する投稿者が広告を挿入できるタイミングを調整・管理することも可能です。これにより、投稿者は動画内で区切りをつけたいタイミングや、視聴者が不快にならないようなタイミングで広告を挿入できるため、最後まで視聴してもらいやすくなります。投稿者にとっても広告を配信する企業側にとってもメリットが大きいといえるでしょう。
ポストロール広告
ポストロール広告とは、動画コンテンツの最後に配信される動画広告です。動画コンテンツが終わってから配信されるため、動画の尺をあまり考えずに挿入できるのがメリットとなります。また、他の動画広告に比べて行動喚起を促しやすく、例えばLPへの誘導や、コンバージョン率を増やしたい場合におすすめの手法です。
ただし、すでに動画コンテンツは終了していることから、広告を見ずにブラウザバックや次の動画に移動してしまうユーザーも多いです。ポストロール広告は離脱される可能性が高いことから、なるべく最初の数秒間でインパクトのある広告を持ってくることが重要となってきます。
アウトストリーム広告
アウトストリーム広告は、インストリーム広告のように動画コンテンツ内に配信されるものではなく、それ以外の場所で再生される動画広告です。例えば、Webサイトやアプリ内で配信されている動画広告、SNSなどに設置された広告枠に表示される動画広告などが該当します。
アウトストリーム広告にも、インバナー広告やインリード広告といった種類に分類できます。それぞれの特徴について詳しく解説していきましょう。
インバナー広告
インバナー広告とは、Webサイトなどの広告枠に出稿できる動画広告です。ユーザーがコンテンツ(サイト内)を見ているかどうかに関わらず、自動的に配信されるという特徴があります。音声は基本的にミュートとなっていますが、クリックすると音声が流れる仕組みです。
インバナー広告は静止画だけのバナー広告に比べて、より多くの情報を伝えられるというメリットもあります。ただし、ユーザーに対して興味を引くような動画でないと、自動的に再生されていても認知獲得には至らない可能性もあるため、動画広告を制作する際には工夫が必要となってきます。
インリード広告
インリード広告とは、Webサイトの記事内や末尾、SNSのフィード間に配信される動画広告です。インバナー広告は視聴の有無を問わず自動的に再生されますが、インリード広告だと画面に表示されない限り自動再生はされません。インバナー広告に比べてユーザーの目にも留まりやすく、さらに動画広告が再生されたとしてもユーザーの行動は阻害されないため、不快な印象を与えにくいというメリットがあります。
インリード広告は、広告枠が設置された場所までスクロールされない限り再生されず、またユーザーが気になる内容でないとすぐにスクロールされて視聴してもらえない可能性が高いです。結末が気になるようなストーリー性のある内容にすることで、最後まで動画広告を視聴してもらえるかもしれません。
動画広告の課金形式
動画広告は主に課金形式で広告費がかかってきます。主な課金形式は、以下の3種類です。
- CPV課金
- CPM課金
- CPC課金
各課金形式について、特徴をご紹介します。
CPV課金
CPV(Cost Per View)課金とは、動画広告の視聴1回あたりの費用を支払う課金形式を指します。広告が再生された回数に応じて費用を課金する仕組みです。単価を求めるには、広告出稿費用÷再生回数で計算します。
再生回数がカウントされる基準はプラットフォームによって異なります。例えば、3秒時点でカウントされる場合もあれば、完全に動画が視聴されたタイミングでカウントされる場合もあるでしょう。
また、CPV課金は入札型と予約型の2種類に分けることも可能です。入札型とは、動画広告を表示する回数を入札形式によって決定する方法を指します。表示される回数に合わせて、その分の広告費を支払うのが特徴です。
一方、予約型は動画広告が再生された回数に応じてその分の広告費を支払うことになります。広告が再生されたときだけ課金されるため、視聴率やエンゲージメントを重視したい場合におすすめです。
CPM課金
CPM(Cost Per Mille)課金とは、広告が表示されるごとに一定金額の広告費を支払う課金形式です。表示回数(インプレッション数)に合わせて広告費が上がっていき、費用が発生するタイミングは1,000回ごとになります。単価の求め方は、インプレッション数÷広告出稿にかかる費用×1,000です。企業やブランドの認知獲得を目的とする動画広告に適した課金形式といえます。
動画広告が視聴されたかどうかに限らず、広告が表示された時点で課金されるため、クリック率が高ければ高いほど単価は割安になっていきます。ただし、逆にクリック率が低くても一定以上のコストはかかってしまうため、注意が必要です。
CPC課金
CPC(Cost Per Click)課金は、広告のクリック数に応じて広告費が課金される形式です。ユーザーが動画広告を視聴しただけでは課金されず、実際にクリックした場合に課金されるため、ユーザーのアクションやコンバージョン率を上げたい場合に適しています。単価の求め方は、広告費÷クリック数によって求められます。
クリックされないと費用は発生しないため、無駄なコストを抑えたい場合にもおすすめです。ただし、CPC課金は競合他社も多く参入するキーワードで出稿すると、入札単価が高騰してしまい、費用対効果とは釣り合わなくなる可能性もあります。また、最低入札単価が設定されている場合、予算をあまりかけられない企業は参入しづらくなるなどのデメリットも考慮しなくてはなりません。
動画広告が配信できる主な媒体
動画広告を配信できる媒体は数多くありますが、それぞれの媒体で投稿できる動画広告のフォーマットや特徴が違ってきます。どのような目的で広告を配信したいのか、誰に向けて配信したいのかなどによって配信する媒体を決めると、より動画広告の効果を高められるでしょう。ここでは、以下の媒体の特徴についてご紹介します。
- YouTube
- TikTok
- LINE
- Webサイト
- アプリ内広告
YouTube
YouTubeは動画配信サイトの中でも、国内外を問わず多くのユーザーが利用している動画プラットフォームです。Googleの調査によると、国内の利用状況において、18歳以上の月間視聴者数が2024年5月時点で7,370万人を超えたと発表しています。
YouTubeは広告のメニューも豊富で、TrueViewインストリーム広告やYouTubeのパートナーサイトやアプリで配信されるアウトストリーム広告、スマホ端末に配信されるバンパー広告などがあります。また、YouTubeのホーム画面最上部に表示される予約型動画広告の「マストヘッド広告」や、サイト右側にある関連動画や検索結果に表示される「TrueViewディスカバリー広告」なども挙げられます。
Facebookは、他のSNSとは異なり実名で登録・利用するSNSになります。実名で登録することになるため、広告を配信する際のターゲティングの精度が高く、ユーザーに適した動画広告を配信しやすいのが特徴です。
Facebookで配信できる動画広告は、フィード広告やストーリーズ広告、インストリーム広告の3種類に分けられます。フィード広告はタイムライン上に表示され、通常の投稿と同じような形式で表示されることから、不快感を与えることなく自然な形で広告を見てもらえます。ストーリーズ広告は縦型のフルスクリーンで動画広告を流すことができ、印象にも残りやすい広告です。インストリーム広告はFacebook内で動画を視聴する際に、再生前後または途中で流れる動画広告を指します。
Instagramは、主に写真や動画などの投稿がメインとなるSNSです。Facebookを手掛けるMeta社が運営していることもあり、Facebookと連携させて広告配信を行うこともできます。
Instagramで動画広告を配信できるのは、フィードとストーリーズの2つです。特にストーリーズはアクティブユーザーが多く、フォロワーが投稿したストーリーズの合間に配信できます。リーチ率も高く、コストも抑えやすい点から活用される機会も多いです。
一方、フィード広告は投稿されたコンテンツの間に表示されます。フォローしている投稿に紛れて広告が配信されるため、自然と目につきやすく、さらに広告にはCTAボタンも設置されていることから、興味を持ったユーザーを自然に自社サイトへ誘導することも可能です。
TikTok
TikTokは、ショート動画の投稿が中心となるSNSです。以前は10代~20代の若年層が多く利用するSNSとして注目されていましたが、近年は利用者の年齢層が上がっています。コンテンツビジネスラボが2023年に実施した「コンテンツファン消費行動調査」によると、TikTokを利用するユーザーの平均年齢は約36歳となっていることがわかりました。そのため、近年は若者だけでなくより幅広い年齢層に向けて動画広告を配信する企業も増えています。
TikTokの動画広告は、アプリを起動した際に全画面表示で動画広告が流れる「起動画面広告」と通常投稿の間に表示される「インフィード広告」があります。また、TikTokならではの動画広告として、ハッシュタグを活用してユーザーに動画投稿を促す「ハッシュタグチャレンジ広告」も挙げられます。
LINE
無料でチャットや通話などが楽しめるLINEは、アプリ内に設けられた広告枠を使って動画広告を配信することが可能です。広告を配信できる場所は19カ所もあり、ユーザーが広告を目にしやすいことから認知獲得にもつながりやすいメリットがあります。
また、ユーザーの性別や年齢、地域などに加え、LINE公式アカウントから取得したユーザーデータの活用や、Yahoo! JAPANオーディエンスリストの追加によって、ターゲティング数の拡充などもあり、より精度の高いターゲティングが可能となっています。
Webサイト
Webサイトに動画広告を配信する場合、以下のアドネットワーク(複数の広告媒体を集めてネットワークを作り、その媒体にまとめて配信する仕組み)を活用することになります。
- Google動画広告
- Yahoo!動画広告
Google動画広告はGoogleが提携するWebサイトに対して配信するアウトストリーム広告です。Googleが提携するサイト・アプリなどは200万以上にも上っており、多くのサイトやアプリに向けて配信することが可能です。もちろん、ユーザーの属性やサイトコンテンツに合わせて広告を配信できます。
Yahoo!動画広告は、Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(YDN)とYahoo!プレミアム広告のアウトストリーム広告・インストリーム広告の3種類から選んで配信することが可能です。YDNにおける代表的な配信先としては、スマホアプリYahoo! JAPANのタイムラインやWebサイト、クックパッドなどのパートナーサイトが挙げられます。
アプリ内広告
アプリ内広告は、アプリ内に設置された広告枠に表示される動画広告を指します。例えばゲームアプリやマンガを配信するアプリ、キュレーションアプリなどで見られる傾向にあります。配信されるタイミングは、画面が切り替わるときや操作するとき、ポイントを受け取るときなどが多いです。
画面全体に表示されるものから、コンテンツの間に出てくるものまで、形式は多岐にわたります。例えばリワード動画広告が挙げられます。
リワード動画広告とは、ユーザーが動画広告を視聴する代わりにリワード(報酬)を与える広告です。例えばゲームアプリでは、一度ゲームオーバーになってしまっても、動画広告を見ることでもう1ゲーム遊べたり、取得できるポイントが倍になったりします。最後まで視聴してもらえるため、商品・サービスの訴求したい部分を詳細に伝えられます。
動画広告を配信するメリット
通常のWeb広告ではなく、動画広告を配信することで以下のメリットが得られます。
- 高い情報伝達力
- 視認性と記憶効果の高さ
- 広いターゲットリーチ
- コンバージョン率の向上
- 効果検証が容易
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
高い情報伝達力
人間は情報を判断する際に五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を活用しますが、そのうち83%を視覚、11%を聴覚が占めています。視覚と聴覚によって90%以上もの情報を受け取ることができるため、静止画によるWeb広告に比べて高い情報伝達力があるといえるでしょう。
また、静止画やテキストだけでは伝わりにくい情報も、動画によって伝えやすくなります。例えば商品画像を見ても、どのように使用するのかいまいち伝わりませんが、動画なら実際に使用する映像も取り入れることで、ユーザーに「その商品を使っている自分」をイメージしてもらえます。商品を使っている自分をイメージしてもらうことで、実際の利用・購入にもつながりやすいです。
視認性と記憶効果の高さ
動画広告は静止画のバナー広告に比べて、動きがあることから視認性が高いとされています。動きのある動画の方がユーザーの目を引きやすく、自然な形で情報を伝えることも可能です。
静止画のバナー広告などでも、インパクトのあるデザイン・キャッチコピーなどを採用すればユーザーの目を引くことは可能です。しかし、いくら目を引いたとしても記憶に残らなければ高い広告効果は期待できません。動画広告の場合、動画を視聴することでその内容と感情がリンクし、脳に記憶されることから長期的に定着しやすいとされています。
広いターゲットリーチ
動画広告はさまざまな媒体で配信でき、多くのターゲットにリーチできる点もメリットの1つです。例えば、SNSに投稿することでユーザーから他のユーザーにもシェアされやすく、そのまま多くのユーザーに拡散される可能性があります。
動画広告が多くのユーザーに拡散されることを「バズる」と呼びますが、仮にバズった場合数万人規模で動画が拡散されることになります。少ない予算でも、おもしろい内容の動画広告を制作することで、高い宣伝効果をもたらすこともできるでしょう。
コンバージョン率の向上
消費者がECサイトから商品を購入する場合、テキストや画像だけでは十分に伝えきれない部分も出てきます。例えば実際の使い方や商品を使ってみてどのように変化するのかなどは、動画だとわかりやすく伝えることも可能です。
動画によって商品のことを十分に理解できたユーザーは、動画の内容と遷移されたLPで紹介されている内容でミスマッチが起こりにくく、離脱も防げるでしょう。その結果、コンバージョン率の向上が期待できます。
効果検証が容易
動画広告は効果検証が容易にできるという点もメリットの1つです。動画広告による効果を検証する指標として、以下の項目が挙げられます。
- インプレッション数(表示回数)
- 再生数
- 再生された時間
- クリック数
- コンバージョン率 など
いずれもユーザーの行動を定量的に測れる指標です。測定が容易に行えることから、PDCAサイクルも回しやすく、改善していくことでより大きな効果も得られるでしょう。
動画広告を配信するデメリット
動画広告の配信には、メリットだけではなくデメリットも存在します。そのデメリットとは、以下のとおりです。
- 制作コストが高い
- 制作と運用に時間がかかる
- スキップされるリスクがある
- ユーザーの再生環境に依存する
- ユーザーにストレスを与える可能性がある
制作コストが高い
動画広告を配信するにあたって、動画制作に一定のコストがかかります。動画の内容や尺などにもよりますが、制作コストの相場は30~200万円程です。配信や運用代行まで外注
する場合、数百万円規模となるでしょう。
動画を内製すれば、制作コストを抑えることが可能です。しかし、その場合は人件費や人材の養育費、制作ノウハウを身につけるために教育費、撮影や編集に必要な機材・ソフトの購入費などのコストがかかります。そのため、内製にしてもそれなりのコストが必要です。
コストを抑えるために低予算で動画を制作すると、クオリティが下がってしまう可能性があります。過度に動画のクオリティが低いと広告に期待する効果が半減してしまう恐れがあるので、予算とクオリティのバランスに考慮して動画を制作することが求められます。
制作と運用に時間がかかる
動画広告は制作の工数が多いため、他のWeb広告よりも制作・運用に時間がかかることもデメリットです。例えば、実写であれば撮影が必要です。実写の場合、必要に応じてロケ地やキャストの選定、撮影場所の下見・下調べといった準備にも時間がかかることがあるでしょう。
アニメーションや3DCGの動画は撮影が不要ですが、原画や3Dモデルの作成工程が発生します。また、動画に必要な素材が集まれば、編集作業が必要です。カットのつなぎ合わせから音楽・エフェクト・テロップの挿入などを行い、1本の動画にまとめていくのにもそれなりの時間がかかります。
撮影や編集の規模にもよりますが、発注から動画が完成するまで1~3か月は見込まれます。テキストやバナー広告と比べて運用開始まで時間がかかることを理解しましょう。イベントに合わせて広告を配信したいといった予定があれば、早めにスケジュールを組んで動画制作に取り組む必要があります。
スキップされるリスクがある
動画広告はスキップされる可能性がある点にも注意が必要です。一定時間の再生後にスキップできる仕様となっている場合、最後まで視聴してもらえない可能性が高まります。特に最後まで見ないとストーリーが伝わらない構成となっていると、成果を上げることが難しくなるでしょう。
最後まで動画を視聴してもらいたい場合、冒頭でユーザーの興味・関心を引き付ける構成やクオリティで制作することが大切です。目的によっては尺の短い動画広告を作成し、スキップ不可の広告として配信するのもよいでしょう。
ユーザーの再生環境に依存する
動画広告の配信では、ユーザーの再生環境に依存するデメリットもあります。配信される動画はオンラインの環境で再生されるため、通信環境が悪いとスムーズに閲覧できなくなる可能性があります。また、動画はデータの容量が大きいため、ページ全体の表示が重くなり、閲覧に不快感を抱かれてしまう恐れもあるでしょう。
広告を動画のみにするとこのようなデメリットが生じてしまうので、テキストやバナーなどの他のWeb広告も組み合わせて、認知度の向上や集客をしていくことが求められます。
ユーザーにストレスを与える可能性がある
動画広告自体、ユーザーにとってストレスと感じてしまうケースもあります。例えば、動画コンテンツを視聴する前や途中に強制的に広告が再生されてしまう場合、コンテンツの視聴を邪魔されることになるので、ストレスになってしまうでしょう。
特にユーザーにとって興味がない広告、おもしろさのない広告となれば不快感を与えてしまいます。その結果、広告のクリックや購買意欲の低下につながる可能性があるでしょう。ユーザーにストレスを与えないためにも動画広告の配信は適切にターゲティングを行い、ターゲットユーザーが興味を持つ動画にすることが大切です。
動画広告の配信効果を高めるための動画作成のポイント
動画広告はただ動画を作って配信するだけでは、認知拡大やコンバージョン率の向上などの期待する成果につながりません。配信効果を高めるためには、ターゲットに合わせてクリエイティブな動画を作成することが大切です。ここで、動画作成で押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
動画広告の目的を明確にする
まずは、動画広告を作成する目的を明確にします。動画広告を作成する目的は、認知度やリピート率の向上、注文数の増加など企業ごとに異なります。これらの課題に合わせて、適切にターゲティングや動画のストーリーを考えていくことが大切です。
目的が明確になっていない状態で動画を作成すると、狙っているターゲットに響かない広告となってしまう可能性があります。内製・外注いずれにしても、目的が定まっていれば動画の内容や方向性、戦略を考えやすくなります。
動画の冒頭に力を入れる
スキップされない動画広告にするためには、冒頭の5秒間に伝えたい情報を取り入れるとよいでしょう。特に伝えたい内容を伝えることで、ユーザーが興味を持って最後まで見てくれる可能性があります。
例えば、動画の結論や内容を伝えたスピード感のある動画にすれば、最後まで一気に見てもらえる状態を作り出すことが可能です。ユーザーに疑問を投げかけたり、共感を与えるような内容を伝えたりして、結末に期待感を与える動画や反応を示してもらえる動画にするのも効果的です。
ストーリー性を重視する
ストーリー性のある動画にすることも重要なポイントです。ストーリー性のある動画は、特徴や機能的価値を伝えるだけの動画と比べて、人に印象に残りやすく、共感を得られやすい特徴があります。そのため、最後まで視聴を促したり、認知度やブランドイメージの向上につながったりする可能性があるのです。
例えば、登場人物にターゲット層とマッチするキャラクター設定してストーリーのある動画にすれば、ユーザーに没入感を与え、動画の視聴を促せます。また、実際に商品・サービスを利用するシーンや利用後のメリットを具体的に伝えられる動画になれば、その後のアクションを促せるでしょう。
商品・サービスができあがるまでの過程や思いが伝わる内容であれば、企業の理解が深まるのでブランディング効果に期待できます。
動画の尺をターゲットに合わせて最適化する
動画広告の尺はわずか15秒の短いケースもあれば、30秒や1分と比較的長いケースもあります。どの尺が適切かは、ターゲットに合わせて考えていきましょう。
15秒の尺であれば、短時間で商品・サービスの魅力を伝えられ、ユーザーもストレスなく広告を視聴することが可能です。盛り込める情報が最低限となりますが、認知拡大を目的にしているケースでは効果に期待できます。
30秒以上となると、ストーリーや説明が丁寧で、商品・サービスなどへの理解を高められる動画が作れます。ただし、尺が長めなので、広告に興味がないユーザーには途中でスキップされる可能性が高いです。そのため、商品・サービスや企業について知りたいと思っているユーザーをターゲットにしている場合に向いているといえます。途中で離脱されないように冒頭からインパクトのある動画にすることが大切です。
CTAの設置を戦略的に行う
コンバージョンにつながる動画広告にするためには、CTAの設置が効果的です。CTAは、「Call To Action」の略語で「行動喚起」を指します。動画の最後に「今すぐ購入する」「資料を請求する」などの目的に合わせてCTAを設置することで、動画を視聴した後にユーザーがアクションを起こしてくれる可能性があります。
CTAがない場合、ユーザーが広告内容に興味を示してくれても、Webサイトに自分で検索してアクセスしなければなりません。その手間からコンバージョンにつながる機会が喪失してしまう可能性があります。それを避けるためにも、広告を視聴したユーザーがスムーズにアクションを起こせるように、CTAを戦略的に設置しましょう。
動画広告と相性のいい業界
動画広告は幅広い業界で活用できます。具体的に動画広告と相性がいい業界は以下のとおりです。
飲食業界
飲食業界は、顧客がWebから情報を仕入れて予約・来店するケースが増えているため、Web広告がよく活用されている業界です。動画なら視覚と聴覚からアプローチが可能なため、飲食店のコンセプトやこだわりをうまく伝えられます。
飲食業界の場合、食材が焼ける音や煮込む音、手間暇かけた調理工程、完成したばかりの料理などを動画にすることが可能です。これらの要素を取り入れた動画は食欲をそそるので、来店を促すきっかけとなってくれます。
食品業界であれば、ブランドの価値に重きを置いてユニークな動画広告を作成するケースが多いです。例えば、有名な人や個性的なキャラクターが出演する動画や展開が気になるストーリー性のある動画であれば、食品やブランドの印象を強く残せます。
不動産業界
不動産業界の場合、動画から物件の魅力をわかりやすく伝えられるので動画広告と相性がよい業界です。動画の場合、文章や静止画よりも一度に多くの情報を伝えられます。
実際の物件の外観や内装、ロケーションを映した動画は、物件の詳細や雰囲気を伝えることが可能です。そのため、動画の視聴をきっかけに物件への問い合わせや入居・購入の申し込みといったアクションを促せます。
図面や写真だけでは伝わりにくい雰囲気、日当たりの良さ、周辺環境なども動画ならわかりやすく伝えられます。実際に現地で案内をしているような動画やナレーション・テロップで物件のおすすめポイントを紹介する動画なら、ユーザーに親近感を与えられます。物件紹介などの動画を公式YouTubeチャンネルで定期的に配信すれば、新たなターゲットの開拓にも期待できるでしょう。
美容・コスメ業界
美容・コスメ業界でも動画広告の活用はおすすめです。ブランドイメージ動画や商品や店舗紹介、商品の使い方・ハウツー動画、消費者のレビューといった、さまざまなジャンルの動画を活用できます。
代表的な動画は、商品や店舗の紹介動画です。コスメに配合されている美容成分や研究結果のエビデンスなどをまとめることで、商品に対する信頼感を訴求できるでしょう。店舗紹介動画なら写真では伝わりにくいお店やスタッフの雰囲気、施術内容などをアピールして、来店を促せます。
商品の使い方を紹介した動画も作成すれば、メイク初心者や使い方に悩むユーザーにとって親切で、ブランドのイメージアップにつながるでしょう。ブランドのコンセプトやストーリーを伝える動画なら、ユーザーに共感してもらいやすくなり、リピーターやファン化につながる可能性があります。
教育・eラーニング業界
地域に密着した学習塾や習い事教室、学校などは、チラシや看板でも集客は可能です。しかし、最近は情報収集にネットが活用されていたり、オンライン上で学習を提供するサービスが増えたりしているため、アナログな手法だけのマーケティングが不十分となっています。そこで動画広告をはじめとしたWebマーケティングが求められています。
教室での授業の様子や生徒・教師(講師)のインタビューなどを動画にすれば、実際の雰囲気や評判を伝えられるので、保護者や生徒が興味を持ってくれるでしょう。塾・学校・e-ラーニングの特徴を紹介した動画や、ストーリー性を持たせたCM動画などで認知拡大・ブランディングを行うことも可能です。
ファッション業界
ファッションアイテムの場合、動画なら着用したときのイメージをリアルに伝えることが可能です。写真と比べてモデルが着用して動くシーンの方が素材の質感や動きやすさ、自分が着たときのイメージがしやすくなります。その結果、「この服が着たい・欲しい」という購買意欲が刺激され、店舗への来店やECサイトへの誘導につながる可能性が高いです。
ファッション業界は、特にX(旧Twitter)やInstagramといったSNSと相性がよいです。SNSで動画を発信することで、画像・動画から商品を探しているユーザーから認知してもらえたり、お気に入りの動画を拡散してもらえたりすることが期待されます。
着回し術やファッションコーディネートの提案といった動画も、おしゃれに関心を持つユーザーにとって魅力的な動画です。参考になる着回しやコーディネートの提案を通じて、商品の売上アップにつながる可能性があります。
エンタメ・ゲーム業界
映画・音楽・ゲームといったエンタメ系の商品・サービスの場合、動画なら音や映像によってダイレクトに魅力を伝えられます。文章や静止画よりも世界観やストーリー、メッセージ性が動画なら表現しやすく、視聴者の印象に残ったり、新規顧客の獲得につながったりする可能性が高いです。
例えばゲームであれば、物語のあらすじや実際のプレイ画面を動画にすることで、どのようなゲームなのかユーザーにわかりやすく伝えられます。動画を視聴したユーザーは、好みのストーリーやゲームシステムなのか判断しやすくなるでしょう。動画が話題になればSNS上で拡散され、手間をかけずに多くのユーザーに認知してもらえます。
旅行・観光業界
旅行・観光業界では、観光地・スポットのPRや宿泊施設・プランの紹介、ツアー紹介などさまざまな用途で動画を活用できます。動画なら短時間で多くの情報を盛り込むことができ、観光地の魅力や雰囲気を詰め込んだ動画は「行ってみたい」という欲求を高めることが可能です。文章や画像だけでは伝えにくい臨場感を届けられることが動画の強みです。
動画広告であれば、YouTubeやSNSなど複数のプラットフォームに発信し、不特定多数のユーザーにアプローチできます。特にSNSであれば拡散性があるので、コストや時間をかけずに効率よく認知を向上できるでしょう。
テクノロジー・IT業界
テクノロジー・IT業界は、パソコンやスマートフォンで使うツールの開発やインターネットを通じてサービスを提供するケースが多く、Web広告と親和性が高い業界です。また、商品・サービスの情報量が多く、テキストや静止画では短時間で説明できなかったり、仕組みや専門用語が難解で内容が伝わりにくかったりする性質があります。
動画の場合、視覚や聴覚を通じて多くの情報を短時間で伝えられます。複雑な技術も映像やテロップ、ナレーションによってわかりやすく表現できるので、商品やサービスの特徴や強みを深く理解でき、ツールやサービスを探しているユーザーの助けとなるでしょう。
健康・フィットネス業界
健康・フィットネス業界の場合、動画を活用すれば商品やサービスの特性や魅力を視覚的に訴求できます。商品紹介動画であれば、エビデンスを含めながら商品の特性や機能、期待できる効果をわかりやすく伝えることが可能です。実際に使用しているシーンを取り入れれば、自分で使うときのイメージがしやすくなり、購買意欲を高めます。
スポーツジムやフィットネスジムであれば、施設紹介やメニュー紹介に動画を活用できます。実際の施設やトレーニングの雰囲気、設備の充実度などをアピールすることで、ユーザーの興味を引けるでしょう。簡単なトレーニング方法やコツなど役立つ情報をまとめた動画はブランディングや認知度向上につなげられます。
動画広告のメリットを把握して、効果の最大化を図ろう
Web広告にはさまざまな種類がありますが、その中でも動画広告はWebマーケティングにおいてスタンダードな広告です。動画は視覚と聴覚の両方から情報を届けることができ、視認性が高く記憶に残りやすい、コンバージョンにつながりやすいなどのメリットがあります。YouTubeをはじめ、各種SNSなど多様な媒体で発信でき、拡散されれば低コストで認知度向上や集客につながることも魅力です。
ただし、動画広告の制作に多大なコストがかかったり、ユーザーにとってストレスにならない動画作りには工夫が必要であったりといったデメリットもあります。誰にどのような目的で広告を発信したいのか明確にし、ユーザーにとって有益・おもしろいと思ってもらえる費用対効果の高い動画を作成することを心がけましょう。
さらに詳しい相談は、「無料相談」より受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。