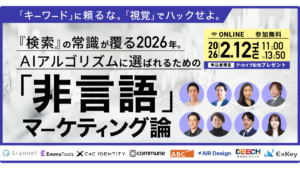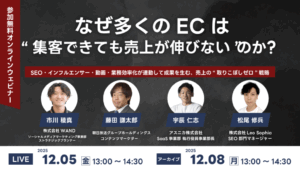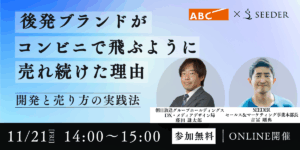【企業アカウント運営者向け】YouTube動画で再生50万超えを狙う10の共通ポイントを解説

こんにちは
朝日放送コンテンツマーケターの藤田です。
今回はズバリ、50万回再生以上を獲得するYouTube動画の創り方をお伝えます。
当社は数多くのYouTubeチャンネルをプロデュースしており、そんな中で、有名人のチャンネルでなくても再生回数50万回以上を獲得した動画がいくつかございます。
それら動画には創るプロセスで共通点が10個ありますので、今回は特別にお伝えします。
先にお伝えしますが「YouTube広告を使いましょう」「インフルエンサーとコラボしましょう」「XやInstagramなどの他のSNSで告知しましょう」という内容ではありません。
これがその動画例の1つです(以下サムネをクリック下さい)
以下の動画は、当社が制作支援し、50万回再生以上を獲得した動画です。
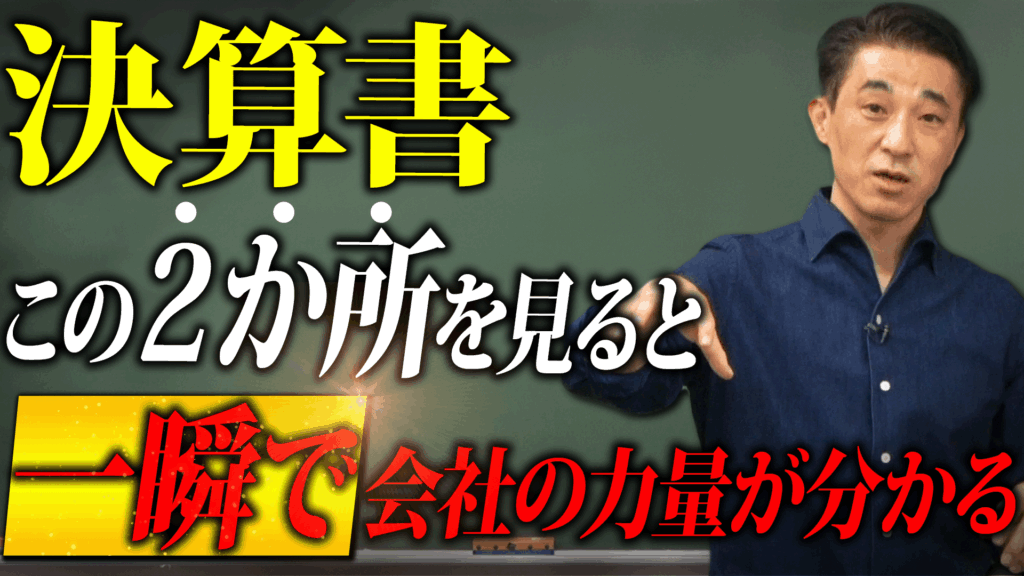
共通点1.YouTube内の視聴者が知りたい事や視たいものをリサーチし、企画のベースにする

これは他の人のWeb記事や動画でも説明されていますが、YouTubeで再生回数を伸ばすためにはマストの部分です。YouTubeで再生回数の伸ばそうと思うと、皆さんどうしても「まだ誰も思いついた事のない斬新な企画」等のブルーオーシャンを求めがちですが、YouTubeにおいては企画段階での発想はそれとは逆の方が良いです。
YouTube内で自社が発信したいと思う内容に付随する様々なキーワードを入れてみて、比較的、再生回数が多い動画が複数本出てくる領域が見つかったら、それこそが「視聴者が知りたい事や視たいもの」です。当社はプロなので様々なツールを使ってこれを調べますが、素人の方でも愚直にYouTube検索をいろんな切り口からやるとパワープレイで実行可能です。
ここで見つけた企画はそっくりそのままパクるという意味ではなく「ベース」にすることが重要です。例えば今回サンプルで出した動画は、本リサーチの結果、決算書に関する内容に視聴ニーズがあると判明しました。但し、決算書と一口に言っても様々な切り口が存在します。その中で「ここを見ると会社の力量が分かる」という切り口をゼロから考えてそのベースの上に乗せて作っています。ここはプロならではの技術と言えます。
共通点2.YouTubeで絶対にやってはダメな企画を先に見定める

YouTubeで伸ばす方法をリサーチしていると「成功しているものをリサーチ」という切り口の意見が多いです。確かにこれも間違っていないのですが、当社がそれ以上に大事にしているのは「失敗している動画の洗い出し」です。本ブログのテーマは50万回再生以上を目指す場合ですが、これはコンスタントには起こりえない事を考えると、何本動画を出しても大滑りしない仕組みを創る事も一方では重要です。
この観点では、まずは失敗している企画をYouTube上で先にしっかり見定めるという工程が必要です。
この作業、やっていただくと分かるのですが、皆さんが元々「やりたい」と思っていた企画の方向性は、既に他の企業が挑戦してくれていて、且つそこは行き止まりであると証明してくれているケースが少なくないです。こういう言い方は良くないですが、過去の人が体を張って行き止まりだと証明してくれたデータはきちんと目を通した方が良いです。ここを見誤って間違った企画をやると、演出やVSEOどうこうの細かい部分以前に、そもそも行き止まりだったというオチが多いです。
共通点3.その企画テーマで「最近伸びている動画」を徹底的にリサーチする

共通点1で再生回数が多い動画テーマがいくつか見つかった際に、1つ注意しなければならない事があります。それはその企画がどういうチャンネルで、いつ投稿されたものか?という事です。
例えば、既にチャンネル登録者数が多いチャンネルが投稿した動画であれば中身の良し悪し以前に一定の再生回数は保証されたもの同然、という事が多いですし、これは当たり前の話ですが、再生回数がいくら多くてもそれが1年前・2年前に投稿されたものであれば、数値通りに「再生回数が多い」とは言えないケースもあります。
何が伝えたいのかと言いますと、皆さんが本当に参考にすべきは、チャンネル登録者数がなるべく少なく、且つなるべく最近アップした動画で再生回数が伸び続けている動画、なんです。これはそういったツールを使えば簡単に分かりますし、通常のYouTube検索でもパワープレイで調べようと思えば調べられます。
共通点4.伸びている動画の動画構成を「参考」にする

参考となる動画が見つかったとして、その後やるべきはその動画の構成を参考にするという事です。
よく台本を一言一句書き起こしてそれをトレースして、というアドバイスも見受けられますが、これはプロがやれば効果はありますが、YouTubeにそこまで詳しくない人がこれをやるのは正直難しいと個人的には思います。
そうではなく、この動画が結局言いたい事はこれで、そこから1つブレイクダウンしてこういう要素を伝えて、さらにその根拠でこれを伝えて、といういわゆるロジックツリーのようなものを参考にすることがとても重要です。実はYouTube上にあるあらゆる動画で、このロジックツリーを1発で出してくれるツールが存在します。当社もそれを使用してそれぞれの参考動画を丸裸にしています。
このロジックツリーを参考にすべきだと当社が考える理由は、YouTubeのアルゴリズムでもおそらく似たような動画解析(ロジックツリー方式)をしていると推測するためです。YouTubeもこういったロジックツリー方式でこの動画はこういう動画とラベリングし、関連動画表示等をさせているものと推測しています。なのでYouTubeのアルゴリズムを小手先で学ぶのではなく、こうやって芯の部分の考え方をしっかり思考として慣れていく事が重要です。
共通点5.喋る人の話し方のキャラクターは事前に綿密に打ち合わせて決めておく

これは誰かが喋る系の動画で、YouTubeをきちんと理解してしまう人がよくやってしまう失敗です。
台本や構成を作って、それをほぼぶっつけ本番で出演者に読ませてしまうのです。
人が喋る動画では「喋る人の話し方やキャラクター」はめちゃくちゃ重要です。全く同じ内容を喋っていても喋る人が違うだけで再生回数が全く違うなんて例はYouTube上ではゴロゴロあります。
なので、話し方やキャラクターは事前にしっかりと綿密に打ち合わせておく必要があるのです。 これは「流暢に喋らないとダメ」という意味ではありませんし「その人にとって無理なキャラクターを演じて下さい」という意味でもありません。その人が一番自然に喋られるというキャラクターがベースにあって、そこから少しずつ微調整をしていくのです。この作業を行うだけで動画は本当に別物になります。喋る人がプロではなく素人の演者であっても、この微調整は絶対にやらないと動画は伸びないです。
共通点6.台本は一言一句ではなく、ポイントだけ設定する

50万回以上の再生回数を獲得する動画の台本は、一言一句書いたものではなく、ポイントだけを設定したものです。これは何を意味するのか?人って、決められた何かを読まされている人の話を聞くのってやっぱり苦痛なんです。それよりも、お喋りが上手じゃなくても自分の言葉で本音で喋っている人の話をより聞いてみようと思います。YouTubeは特にその傾向が強いです。なので、台本はポイントだけしっかり設定して、自由に喋るべきところは自由に喋るスタイルの方が間違いなく動画は伸びやすいです。
一度、すごく伸びている動画をいくつか見てみて下さい。動画内容で「これは明らかに台本じゃないよな」と思われるやり取りが必ず頻発している動画が多い事に気づくと思います。
再生回数が伸びている動画ってそういう事なんです。
共通点7.ジャンプカットは一定のリズムを刻む

ジャンプカットというのは、喋っている間の変な“間”を編集でカットする事をさします。無言の間もそうですし「えーっと」のような話の本筋とは関係のない発言部分もそのカット対象です。
このジャンプカット、単にやればやるほど余計な間が消えて良い、というものではなく、人が聞いていて「心地よい」と感じる一定のリズムとなるように調整する事が大事です。
当社のサンプル動画やその他の再生回数を得ている一部の動画を視てみて下さい。
メトロノームのように正確に一定のリズムを刻んでいるわけではありませんが、原則は一定のリズムで人が聞いていて違和感ないように編集されているはずです。これがプロの技です。
共通点8.余計な演出と宣伝色は極力そぎ落とす

冒頭にハイライトがあって、オープニングトークがあって、ロゴを使ったアニメーションがあって、サウンドエフェクトがバンバン入って・・・・・テレビ番組さながらの動画コンテンツがYouTubeで受けていた時代はありました。ただ、今はこういった演出の動画は増えてきています。また、そもそものYouTube内の視聴者としてこういう「いかにも」みたいな演出は見ていて疲れる印象を持つ人が増えてきているのです。ではどうすべきか?答えはシンプルです。なるべく余計な演出をせずに伝わるような動画内容とするのがベストです。
何か演出を付け足していくのではなく「なるべく演出しないでもストレスなく視聴できるか?」これを突き詰める事が重要です。余計な演出はしないですが、その代わり、前述のリズムであったり音質であったり、構成であったり、ここはとことん突き詰めないと勝てません。
また、これは当たり前ですが、企業の宣伝色は動画からは削ぎ落さないと再生回数は伸びません。宣伝色を付けても再生が伸びるのは、そのチャンネルが既に有名である場合に限定されます。ここはぐっと我慢が必要です。
共通点9.サムネイルは心理学で創る

サムネイル創りはYouTubeでめちゃくちゃ重要です。
良いサムネイルを創らないと、そもそも動画を視てもらえないからです。他のWeb記事で書かれているように、他の人のサムネイルを参考にするという事は大いにやるべきです。ただ、他の人で成功しているサムネイルをそのまんまパクるというのは違法ではありませんが、そのやり方には正直限界があります。理由は「なんでそのサムネイルが成功しているのか?」を全く理解せず、見様見真似しているだけなので、応用が利かないのです。
サムネイルのように極めて小さい面積の中に文字・イラスト・画像等が配置されている、発信できる情報は限られている中で人をいかに興味喚起するかは、これはもう心理学の範疇です。
大切なのは成功しているサムネイルに対してしっかりと自分なりの「仮説」を持つということです。
これはこういう事をやったからクリックされているんじゃないかという仮説です。
ちなみに、冒頭で表示した当社のサムネイルは、サムネイルのセオリーから言うとあまり良くないとされるものです。文字数は純粋に多過ぎますし、「決算書」「2か所」「一瞬」と伝えたいポイントも複数入っており、しかもそれぞれ強調の仕方が異なっています。これは一般的にはサムネイルでは「あまりやらない方が良い」とされる事です。ただ、当社はそんな事は分かっていてわざとこのサムネイルにしています。それは当社が他の人の成功しているあるサムネイルを見て、ある仮説を持ったからです。
共通点10.立ち上がり・企画構成・サムネイル、この3点セットこそプロに外注

よく、YouTubeをなるべく外注せず内製化でやりたいという企業様からの相談を頂戴します。
私も以前、経営者をしていましたのでそういう発想はとてもよく理解できます。なるべく余計なコストをかけずにYouTubeを運用したいと思うのは企業としては当たり前の事です。
ただ、YouTubeで本当にしっかりとチャンネルをグロースさせたいのであれば、コストをかけるべきところはかけて外注しないと本当に勝てない世界です。
当社が考える「絶対に外注しないと勝てない領域」は以下の3つです
・チャンネルの立ち上がり
・動画の企画構成
・サムネイル創り
この3つを外注した方が良い理由はシンプルで、上記3つは実際にYouTube上で複数チャンネルを運用した経験が無いと良し悪しが分からない部分だからです。こういう経験有無の差が成否を分ける部分がこの3つだと言い換えられるかもしれません。なので、しっかりとチャンネル運用経験がある会社に上記3つは依頼する事は腹をくくる必要があります。