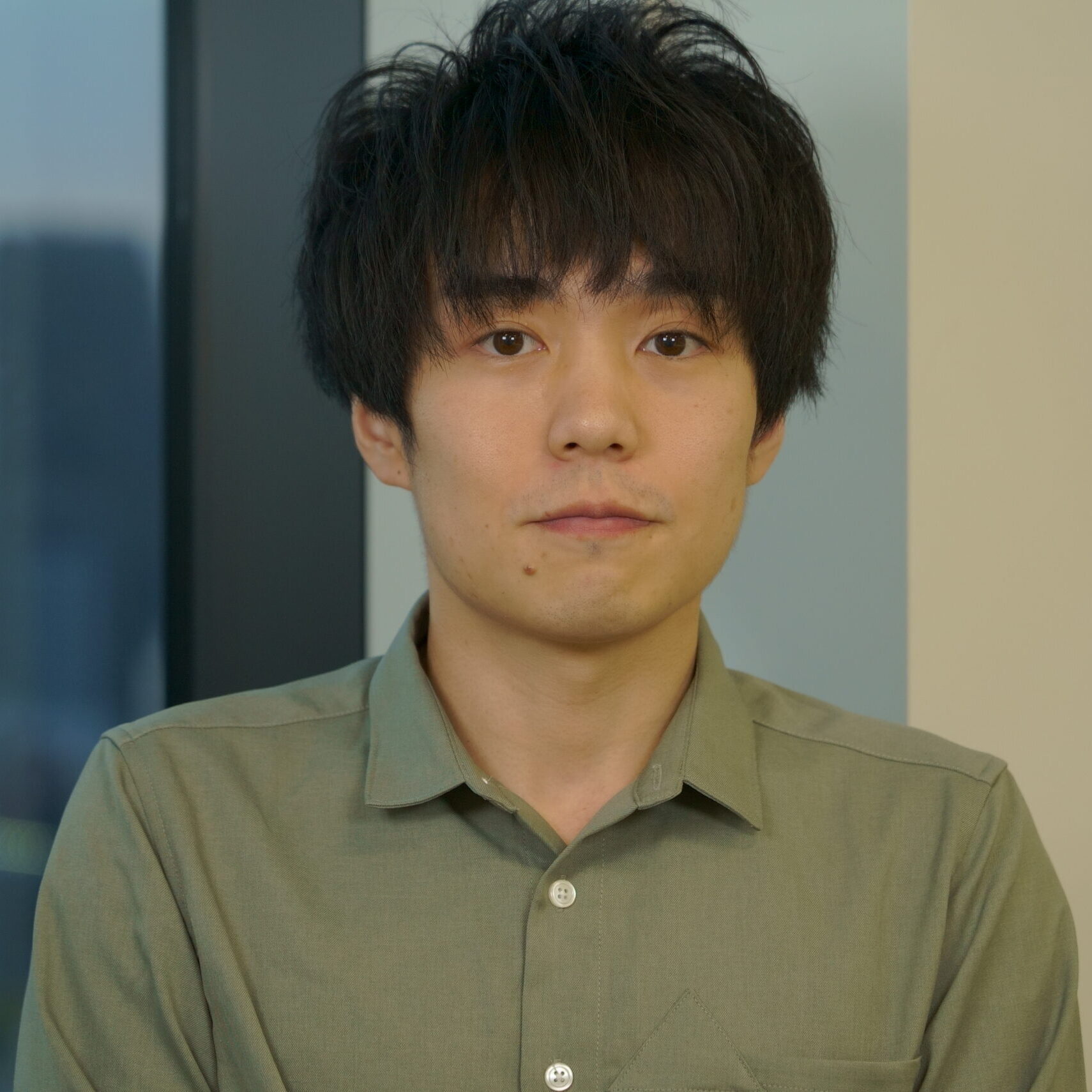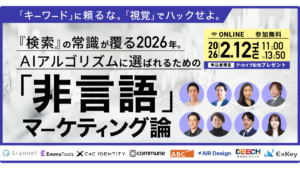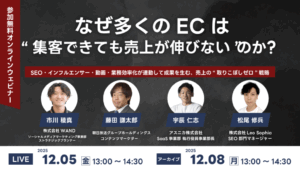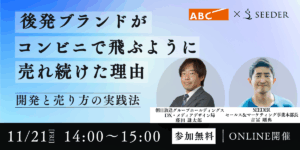動画制作の著作権を徹底解説!知らなかったでは済まない注意点とは?

企業のプロモーションから個人の情報発信まで、動画の活用シーンはますます広がっています。しかし、魅力的な動画を制作する上で、見落としてはならないのが「著作権」の問題です。「知らなかった」では済まされない著作権の知識は、動画制作に関わる全ての人にとって必須と言えるでしょう。
この記事では、動画制作における著作権の基本的な考え方から、具体的な注意点、さらには外部へ制作を依頼する際のポイントまで、網羅的に解説します。
動画制作と著作権の基本
動画コンテンツがビジネスや情報発信において重要な役割を担う現代、著作権の理解は動画制作者にとって不可欠です。意図せず他者の権利を侵害してしまうと、法的なトラブルに発展するだけでなく、企業や個人の信用を大きく損なう可能性があります。このセクションでは、動画制作に関わるすべての方が知っておくべき著作権の基本的な知識について解説します。
【内部リンク】初心者でも簡単!動画制作の基本とコツをマスターしよう | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」
著作権とは何か?分かりやすく解説
著作権とは、小説、音楽、絵画、映画、写真、コンピュータプログラムといった「著作物」を創作した人(著作者)に法律上与えられる権利のことです。この権利は、作品が創作された時点で自動的に発生し、特許権や商標権のように申請や登録をする必要はありません(無方式主義)。
引用:著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。動画も、撮影された映像や編集されたコンテンツが創作的な表現物と認められれば、著作物として保護されます。具体的には、映画、テレビ番組、プロモーションビデオ、YouTube動画などが該当します。
著作権には、大きく分けて「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種類があります。
- 著作者人格権: 著作者の人格的な利益を保護する権利で、公表権(作品を公表するかどうか、いつどのように公表するかを決める権利)、氏名表示権(著作者名を表示するかどうか、どのように表示するかを決める権利)、同一性保持権(作品の内容や題号を勝手に改変されない権利)などがあります。これらは著作者固有の権利であり、他人に譲渡することはできません。
- 著作権(財産権): 著作物を利用することで得られる財産的な利益を保護する権利です。複製権、上演権、演奏権、公衆送信権(インターネットでの配信など)、譲渡権、貸与権などが含まれます。こちらは他人に譲渡したり、利用を許諾したりすることが可能です。
引用元:著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
動画の著作権は誰に帰属するのか?
動画の著作権が誰のものになるかは、その動画がどのように作られたかによって変わってきます。
例えば、個人が一人で動画を制作した場合、原則としてその制作者自身が著作権を持つことになります。一方、会社のような法人の従業員が業務として動画を作成した場合は、一定の条件を満たせば、その法人が著作者として権利を有します。外部の制作会社に委託して動画を作ってもらうケースでは、契約内容によって著作権の帰属が決まるのが一般的です。また、複数人で協力して動画を制作した場合は、関係者全員が共同で著作権を持つこともあり、その場合は権利の行使が複雑になることもあります。
後のトラブルを避けるためにも、動画制作を始める前に、契約などで著作権の所在をはっきりさせておくことが非常に大切です。
引用元:文化庁トップページ | 誰でもできる著作権契約
著作権侵害となるケースとは?
著作権侵害とは、権利を持つ人の許可なく、著作権法で守られている作品を利用する行為を指します。動画制作の場面では、いくつかの典型的な著作権侵害のケースが考えられます。
例えば、他人が作った映画やアニメ、音楽などを無断でコピーして自分の動画に使ったり、インターネットにアップロードしたりする行為は許されません。これは、たとえ短い一部分であっても同様です。また、市販のCDやダウンロードした楽曲をBGMとして無断で使用することや、インターネットで見つけた写真やイラストを許可なく動画内に取り込むことも著作権侵害にあたります。
これらの行為は、個人的な利用や非営利目的であっても、法的な責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
【内部リンク】動画制作でこれはダメ!やってはいけないこと5選 | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」
著作権と混同しやすい権利(肖像権・パブリシティ権)
動画制作においては、著作権以外にも注意すべき権利があります。特に混同しやすいのが「肖像権」と「パブリシティ権」です。
- 肖像権: 人がみだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、公表されたりしない権利です。これは法律で明文化されているわけではありませんが、判例で認められている人格権の一つです。街頭インタビューやイベント撮影などで個人が特定できる形で撮影し、本人の許可なく動画を公開すると肖像権侵害となる可能性があります。
- パブリシティ権: 有名人(タレント、スポーツ選手など)の氏名や肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を排他的に利用する権利です。有名人の写真や映像を無断で商品広告やプロモーション動画に使用すると、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。法律に条文として明記されている権利ではなく、主に裁判所の判例を通じて確立されてきた権利です。
引用元:文化庁(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/pdf/94081601_01.pdf)
著作権が「創作された表現物」を保護するのに対し、肖像権は「個人の容貌や姿態」、パブリシティ権は「著名人の経済的価値」を保護する点で異なります。動画制作では、これらの権利にも配慮し、必要に応じて許諾を得ることが不可欠です。
動画制作で著作権侵害をしないための具体的注意点
動画制作の過程では、様々な素材を利用します。音楽、画像、映像など、これらの素材には著作権が存在する可能性があり、不用意な利用は著作権侵害につながりかねません。ここでは、著作権侵害を未然に防ぐための具体的な注意点を解説します。
音楽・BGM利用時の著作権の確認方法
動画の雰囲気を大きく左右する音楽やBGMですが、利用する際には著作権に細心の注意を払う必要があります。日本国内の多くの楽曲は、JASRACやNexToneといった著作権管理事業者が管理しており、これらの楽曲を使用する場合は、利用目的(例えば、個人での視聴か、広告などの商用利用か)に応じて、所定の手続きと使用料の支払いが必要です。
「著作権フリー」と表示されている音源でも、完全に自由というわけではなく、多くは一度料金を支払えば追加料金なしで使える「ロイヤリティフリー」の形態です。この場合も、商用利用が可能か、制作者のクレジット表記が必要かなど、利用規約をしっかり確認しましょう。
また、個人的に購入したCDや配信音源を無断でBGMに使うことは原則できませんので、アーティストやレコード会社への許諾確認が求められます。
【内部リンク】YouTubeショートの音楽と著作権について:収益化できる?違反にならない? | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」
画像・映像素材利用時の著作権の確認方法
動画制作で画像や映像素材を使う際も、著作権の確認は欠かせません。有料や無料のストック素材サイトから入手したものは、各サイトの利用規約を必ず守りましょう。
他人が制作した映画やテレビ番組、YouTube動画などは著作物ですので、無断でその一部または全部を利用することはできません。インターネット上で見つけた写真やイラストも同様に、制作者に著作権があるため、無断使用は避け、許可を得るか、利用規約に基づいて使える著作権フリー素材を選びましょう。
自分で撮影・制作した素材ならば基本的には問題ありませんが、人物が写っていれば肖像権、特定の建物や美術品が対象であればそれらの権利にも配慮が必要です。
「引用」の正しいルールと範囲
著作権法では、一定の条件を満たせば、著作者の許可なく他人の著作物を利用できる「引用」というルールが定められています。しかし、この引用が認められるためには、いくつかの重要な条件を全てクリアしなければなりません。
まず、引用する著作物は公表済みである必要があり、未公表のものは引用できません。また、自分の主張を補強するためなど、引用する必然性が求められます。そして、引用する部分が自分の作品の中で従たる(補足的な)役割であり、質・量ともに自分の作品が主であることが必要です。引用箇所は明確に区別し、誰の何という作品から引用したのか、出所をきちんと示すことも義務付けられています。
これらの条件を満たさない安易な利用は、著作権侵害となるリスクが高いので注意が必要です。
フリー素材の利用規約は必ず確認
「フリー素材」という言葉を聞くと、何でも自由に使って良いように思いがちですが、実際には利用するための条件が細かく定められていることがほとんどです。そのため、利用する前には必ず利用規約を確認することが大切になります。
具体的に確認すべきポイントとしては、まず、その素材をビジネス目的の動画で使用できるかという「商用利用の可否」が挙げられます。また、動画内や説明欄に制作者名やサイト名を記載する必要があるかという「クレジット表記の要否」も重要です。さらに、サイズ変更や色合いの調整といった簡単な編集以上の「加工・改変が許可されているか」も確認が必要です。ウェブサイト限定や印刷物限定といった「利用できる媒体に制限がないか」といった点も、見落とせません。
これらの利用規約を読まずに使ってしまい、後からトラブルに発展するケースは残念ながら少なくありません。
屋外撮影時の背景の写り込みへの配慮
屋外で動画を撮影する際、背景に建物、看板、ポスター、キャラクターなどが意図せず写り込んでしまうことがあります。これらが著作物である場合、原則としてその権利者の許諾なしに公表すると著作権侵害となる可能性があります。
ただし、著作権法では、撮影対象物から「分離することが困難」な付随的な著作物は、一定の条件下で許諾なく利用できるとする規定があります(いわゆる「写り込みに係る権利制限規定」)。しかし、この規定が適用されるかどうかは、写り込みの程度(大きさや識別可能性)や、その著作物の種類、利用態様などによって個別に判断されるため、一概に「大丈夫」とは言えません。
引用元:いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について | 文化庁
動画制作を外注する際の著作権トラブル回避術
自社で動画を制作するリソースがない場合や、より専門的なクオリティを求める場合、外部の制作会社やフリーランスのクリエイターに動画制作を委託することは有効な手段です。しかし、外注する際には著作権に関する取り決めを明確にしておかないと、トラブルに繋がる可能性があります。
契約書で必ず確認すべき著作権の帰属条項
動画制作を外部の会社やクリエイターに依頼する際に、最も気をつけておきたいのが、完成した動画の著作権が最終的に誰のものになるのかを契約書ではっきりと定めておくことです。法律では、基本的に作品を創作した人が著作者となり著作権を持つため、契約書に特別な記載がなければ、動画の著作権は制作会社側に帰属するのが一般的です。
もし依頼主である発注者側が著作権を持ちたいと考えるのであれば、契約書の中に「制作会社は、完成した動画に関する全ての著作権を、納品と同時に依頼主に譲渡する」といった内容の条項を必ず盛り込む必要があります。さらに、著作権が譲渡された後も著作者の人格的な権利(著作者人格権)は制作者に残るため、依頼主が動画を自由に改変したり利用したりできるようにするためには、「制作会社は著作者人格権を行使しない」という特約を加えることが望ましいでしょう。
引用元:文化庁トップページ | 誰でもできる著作権契約
二次利用の範囲と追加費用の確認
制作した動画を、当初想定していた用途以外(例えば、ウェブサイト用に制作した動画をイベントやCMでも使用するなど)で利用することを「二次利用」といいます。
著作権が制作会社に帰属している場合、あるいは利用許諾の範囲が限定されている場合、二次利用する際には改めて制作会社の許諾が必要となり、追加のライセンス料が発生することが一般的です。
契約時には、将来的にどのような二次利用の可能性があるかを制作会社に伝え、その際の条件(許諾の要否、追加費用の有無や金額)についても事前に取り決めておくことがトラブル防止に繋がります。可能であれば、想定される二次利用の範囲をあらかじめ契約内容に含めておくのが理想的です。
制作会社が持つべき権利処理の知識と体制
動画制作においては、BGM、画像、フォントなど、様々な素材が使用されます。これらの素材が第三者の著作権を侵害していないか、適切に権利処理されているかを確認することは非常に重要です。
制作会社を選定する際には、過去の実績や評判だけでなく、権利処理に関する意識や体制についても確認することをおすすめします。見積もりや打ち合わせの段階で、使用する素材の権利処理について具体的に質問してみるのも良いでしょう。
動画公開・制作における具体的な著作権対応
動画制作を進める中で、著作権に関して疑問が生じることは少なくありません。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
YouTubeへの動画投稿と著作権について
YouTubeは、世界中で多くの方が動画を公開したり視聴したりする巨大なプラットフォームです。手軽に利用できる反面、著作権侵害のリスクも常に意識しておく必要があります。
YouTubeには「Content ID」という独自のシステムがあり、アップロードされた動画が、著作権者によって登録されている音楽や映像などのコンテンツと一致するかどうかを自動で照合しています。もし一致した場合は、著作権者の設定に基づき、動画がブロックされたり、動画から得られる収益が無効化されたり、あるいは著作権者に収益が分配されたりすることがあります。
安全に動画を投稿するためには、YouTube自体が提供している「YouTubeオーディオライブラリ」にある無料の音楽や効果音を利用する方法があります。または、権利処理が明確になされている素材サイトから、利用規約をきちんと守った上で素材を入手して使用するのが賢明な対処法と言えるでしょう。
社員を動画に出演させる場合の注意点
会社の採用動画や社内イベントの記録などで、自社の社員の方に動画へ出演してもらうケースはよく見られます。
最も重要なのは、社員の方の肖像権の確認です。社員であっても、本人の同意を得ずに容姿を撮影し、その動画を公開することは肖像権の侵害にあたる可能性があります。そのため、必ず事前に動画の利用目的、公開する範囲、公開する期間などを丁寧に説明し、書面で同意を得ておくことが望ましいでしょう。
もし著作権を侵害してしまった場合の対処法
どれだけ細心の注意を払っていても、意図せずに著作権を侵害してしまう可能性は残念ながらゼロではありません。万が一、著作権侵害を指摘されたり、あるいは侵害の事実に気づいたりした場合は、迅速かつ誠実に対応することが何よりも重要となります。
まず行うべきは事実確認です。本当に著作権を侵害しているのか、動画のどの部分が、誰のどの権利を侵害しているのかを正確に把握する必要があります。契約書や利用規約、関連する法令などを確認しましょう。
次に、弁護士や弁理士など、著作権に詳しい専門家に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。専門家の意見を聞くことで、適切な対応方針を立てることができます。
著作権侵害の事実が確認された場合、またはその可能性が高いと判断した場合は、速やかに該当する動画やコンテンツの公開を停止し、削除する措置を取ります。
その後は権利者との間で、損害賠償や今後の対応について協議を行います。ここでも誠意ある対応を心がけ、円満な解決を目指しましょう。
まとめ
動画制作における著作権は、クリエイティブな活動を行う上で避けては通れない重要なテーマです。この記事では、著作権の基本的な考え方から、音楽や素材の利用、外注時の注意点、そしてトラブル発生時の対処法まで、幅広く解説してきました。
著作権の知識は、単に法的なリスクを回避するためだけでなく、他者の創作活動を尊重し、健全なコンテンツ制作環境を育むためにも不可欠です。動画を通じて情報を発信する際には、常に著作権への意識を持ち、適切な権利処理を心がけましょう。
動画制作や広告制作に関するご相談はこちら▶無料相談 | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」
Youtube動画、テレビCM、ブランディング動画などその他さまざまな動画制作についてのご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。
動画支援について詳しくはこちら▶動画支援 | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」